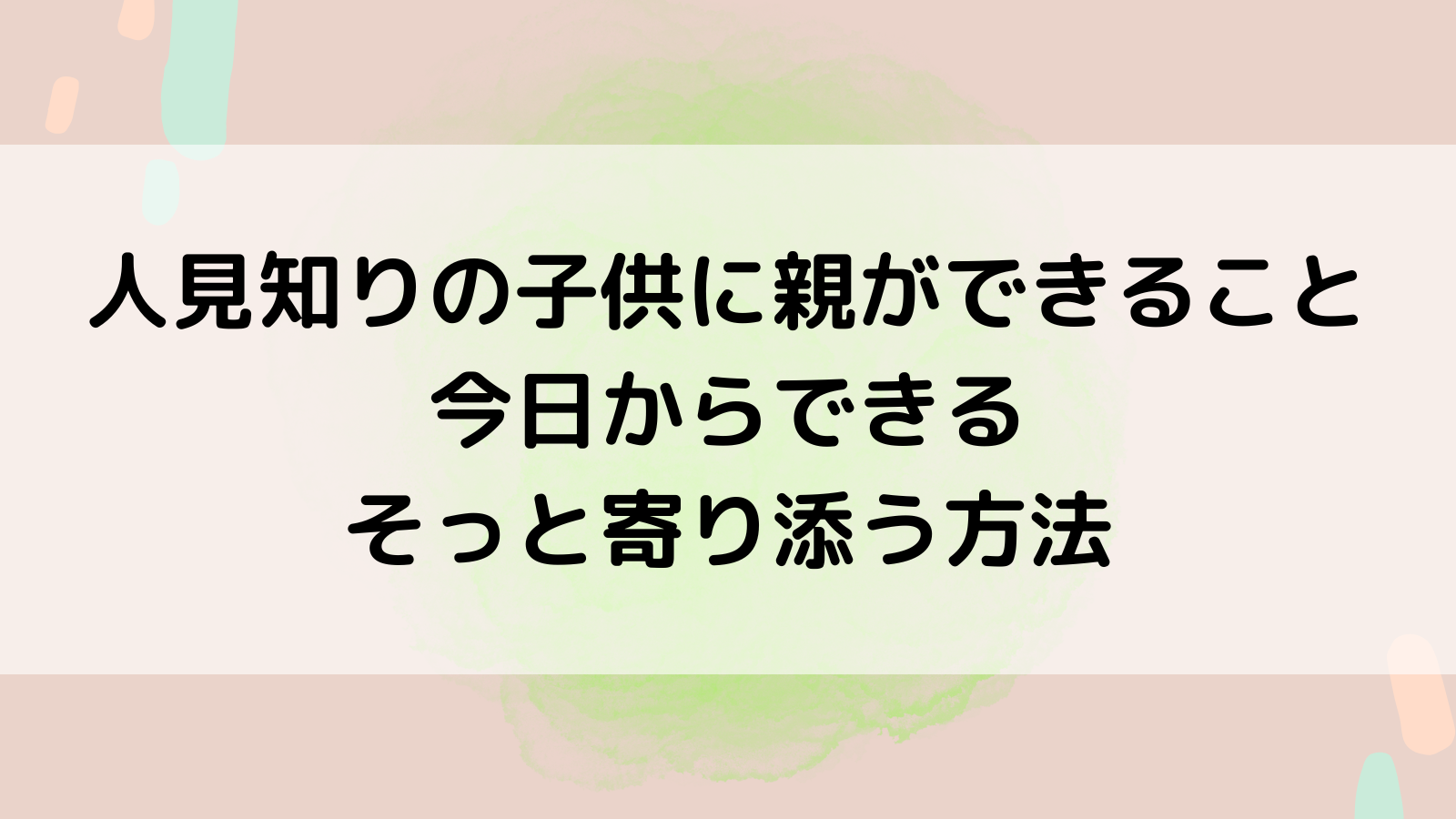子どもが「友達ができない」と悩んでいるとき、親としてどう関わればいいのか——。
正解が分からず、ついアドバイスしてしまったり、逆に何もできずに悩んでしまったりすることもあると思います。
この記事では、人見知りな子どもに対して、親ができる寄り添い方について、私自身の経験も交えながらお話しします。
「つい口を出してしまう」「見守りたいけど難しい」そんな思いを抱えている方に、少しでもヒントになれば嬉しいです。

こちらは、高学年以降向けと思って書きました。

低学年、中学年の頃はもう少し近い距離感でした
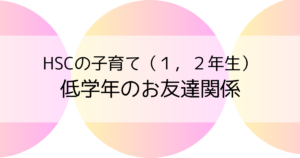
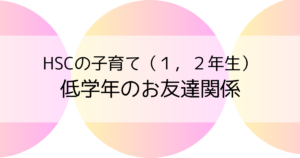
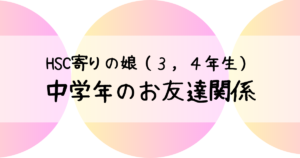
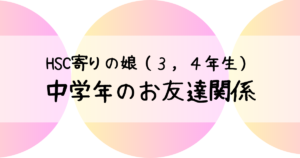
親ができることには、限度がある
アドバイスよりも「安心感」の方が大切
子どもが人間関係に悩んでいるとき、親としては何か解決策を与えたくなります。



私はいつもそうでした。解決してあげなくちゃ!と思考を巡らせていました。
けれど、子どもにとって本当に必要なのは「答え」ではなく、安心して悩める居場所かもしれません。
親がすぐに行動を促したり、アドバイスを与えたりすることで、かえって「今の自分じゃダメなんだ」というメッセージとしてつたわってしまいます。
自己肯定感をダダ下げしてしまうことになりかねません。
親の視点と子どもの視点は、まったく違う
親が「自分ならこうするのに」と思っていても、子どもにはその方法が合わない場合も多くあります。



そもそも、性格が違うんですよね・・・
特に人見知りの子どもにとっては、少しのことでも「自分から話しかける」「輪の中に入る」という行動自体が、大きなハードルなのです。



親のアドバイスは大きなプレッシャーだと気が付きました
私自身も、答えをもらったことはなかった
思い返してみれば、私も子どもの頃、友達付き合いが得意ではありませんでした。
今となっては、コミュ力高いね(おばけ)とまで言われていますが、小学校の低学年まで友達を作るという行為に試行錯誤していたことを思い出しました。



いじめられていたこともありました・・・
でもその頃、親にアドバイスされた記憶は全くなく、自分なりに考えたり、ちょっと勇気を出してみたり…そうやって少しずつ人との距離をつめていきました。
いじめられていた時ですら、親に相談したりはしませんでした。この話はまた別のブログで話しますね。



つまり私自身が最初からコミュ力があったわけではなく経験から学んだことだったんです。
子ども自身の成長のチャンスを奪わない



私の両親は二人とも私を信じて信頼してくれていました
親としてできる一番のサポートは、「どうすればいいか」を教えることではなく、「自分で考え、選ぶ力を信じてあげること」だと確信しました。



そして何よりも温かい笑顔でいてあげることではないでしょうか
見守ることで、子どもが自ら人との関わり方を学び、壁を越える力を身につけていく。それこそが、長い目で見たときに、最も大きな支えになるのではないでしょうか。
親は“助け舟”ではなく、“灯台”のような存在に
見守る強さを持つということ
子どもの人間関係の悩みは、親にとっても苦しい問題です。



本当にこれが一番苦しい‥
それでも、「手を出さないこと」「言いすぎないこと」「焦らないこと」を意識することで、子どもは安心できる環境の中で、自分なりの道を探せるようになるんですよね。
【今日からできる小さな寄り添い方】
- アドバイスではなく「気持ちを聞く」ことを意識する
- 無理に状況を変えようとせず、日常の中でわが子を信じて見守っていく
- 子供から話すまで親からは聞き過ぎない
- アドバイスを求められたときだけ自分の経験を話してみる
- ドンと構えて「大丈夫」という気持ちで子供をみる
おわりに:信じて、見守るという愛し方
小学校も高学年になっていくと、親の目の届かない環境の中で成長していっていきます。



この時が少し距離を保ちながら見守るチャンスかもしれません
私たちにできるのは、「困ったときには戻ってこれる場所」を整えておくことだと思います。
子供が悩んでいそう、悲しそう、つらそう・・・と思った時にもひとまず距離をおいたまま、我が子の今後の人生を歩む第一歩だと信じて、見守っていきたいと思います。
今日もそっと寄り添いながら、子どもが自分の力で世界を広げていくのを見守っていきたいですね。